超音波医学の進歩を世界に発信する:医療に貢献する超音波検査
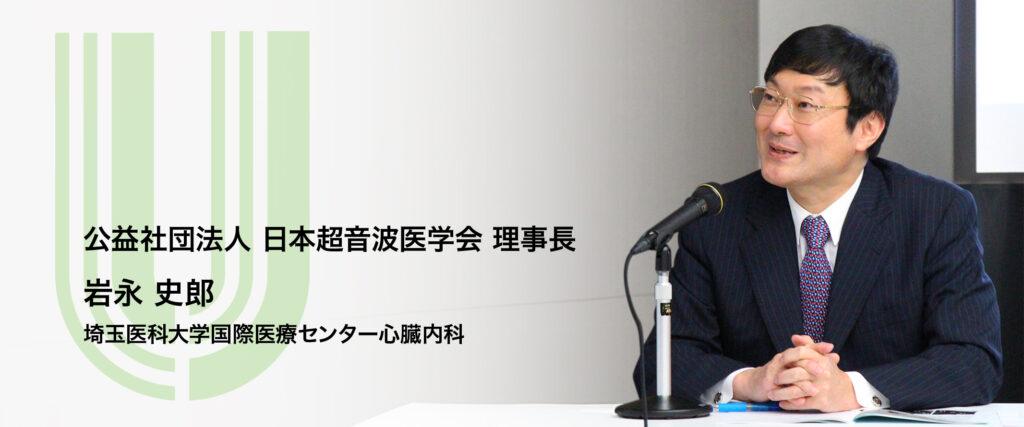
公益社団法人日本超音波医学会は、超音波検査の研究・開発および医学分野での臨床応用を推進する学術団体です。工学研究者、医師、メディカルスタッフなど多彩な人材が所属しています。超音波検査は医療の様々な領域で広く利用され、健康診断、妊娠・出産、がんの診断・治療、心血管手術を含め多くの医療分野で欠かさざる検査となっています。超音波医学の分野で、新しい検査法・治療法の開発、医療への応用を進める研究者や医療関係者を育成するための場でもあります。
身体のなかの血液の流れを画像として可視化するカラードプラ法は、日本の研究者によって開発され、1982年に世界超音波医学会(WFUMB)で初めて報告されました。私は1985年に医学部を卒業しましたが、当時、大学にはカラードプラ像を記録できる超音波診断装置はありませんでした。心臓超音波検査がない時代に心臓病は聴診などの身体診察、心電図、胸部X線写真、心臓カテーテル検査で診断されていました。しかし、カラードプラ法が広く普及すると、心臓病の多くが超音波検査で診断できるようになりました。現在では、診断のみではなく、重症度評価、手術適応の判定、治療中のガイドなど、心臓病診療のあらゆる面で超音波検査が活躍しています。
組織の硬さを画像化するエラストグラフィは、当学会の元理事長である椎名毅博士を中心として研究開発・臨床応用が行われてきました。1990年ごろから開発が進められ、2003年には市販の超音波診断装置に装備されました。現在では、乳腺や肝臓の領域で臨床応用され、種々の病気の診断や評価に役立っています。超音波映像下穿刺手技(肝胆道領域)や3次元超音波法(産科領域)も日本で開発されました。子宮内の胎児を鮮明に観られるのも、身体に医療用の針を安全に刺せるのも超音波検査のおかげです。このように、超音波医学の分野では日本から研究の成果が発信され、日本で臨床応用が進み、世界で評価された技術が多くあります。日本超音波医学会はこのような活動を支援しています。
1965年に設立された当学会は、超音波専門医、超音波工学フェローや超音波検査士などの教育・認定制度、研究者への助成制度を作り、若手の医師や臨床検査士などのメディカルスタッフ、工学研究者の育成にも力を入れています。医療の地域格差が問題視されていますが、超音波検査は小型の装置で、短時間に、医師一人で行えるため、日本の地域医療の問題を解消するひとつの有力な手段であるといえます。専門医・専門技師制度の拡充に力を注ぎ、超音波検査が日本国民の健康増進に役立つように活動しています。
