経時的な左室壁運動変化を呈したTrousseau症候群に伴う非細菌性血栓性心内膜炎(NBTE)の一例
はじめに
この度は、日本超音波医学会第97回学術集会で新人賞という栄誉ある賞を賜り、誠に光栄に存じます。この受賞は、日々の診療でご指導いただいた先生方、並びに熱心に議論を交わし切磋琢磨してきた同僚のおかげです。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。
今回、私が発表し評価いただいた症例は、Trousseau症候群に伴う非細菌性血栓性心内膜炎(NBTE)の一例であり、経過中に左室壁運動が劇的に変化した貴重な一例です。この症例を通して得られた学びを、今後の診療に活かしていくとともに、この経験を共有することで、NBTEの早期診断と適切な治療に貢献できれば幸いです。
患者は57歳女性。主訴は頭痛、めまい、倦怠感でした。工場作業中に頭痛が出現し、翌日には頭痛、倦怠感の増悪に加え、嘔気、歩行困難が出現したため当院受診しました。既往歴は特記すべき事項はなく、バイタルサインは安定していましたが神経所見でBarre徴候が左側で陽性で、左上肢麻痺に対する病識が乏しく、左方への注意力の低下が疑われました。血液検査ではトロポニンIの上昇とともに心筋逸脱酵素の上昇が認め、D-dimerは219μg/mlと高値を示し、腫瘍マーカーの上昇も認めました。心電図でV1、2誘導の陰性T波を認めました。経胸壁心エコー図検査では、左室心尖部および前壁基部から中部にかけて壁運動異常を認め、左室駆出率(LVEF)は45%と軽度低下していました。経食道心エコー図検査では、僧帽弁前尖・後尖に最大径10mmの疣腫を認め、それに伴う中等度の僧帽弁閉鎖不全(MR)を認めました。頭部MRI検査で多発性の急性期脳梗塞像を認めましたが、MRAでは明らかな有意狭窄は認めず、造影CT検査では多発脾梗塞、腎梗塞とともに骨盤内に嚢胞性腫瘤を認め、内部に充実成分を伴うことから卵巣腫瘍が疑われました。冠動脈CT検査では明らかな狭窄病変は指摘されなかったものの、心尖部と心室中隔基部に造影不良域を認めました。
腫瘍マーカーの上昇を伴う卵巣腫瘤、D-dimerの上昇を伴う多発塞栓、血液培養3セット陰性であり、心腔内の疣腫はTrousseau症候群に伴うNBTEを強く疑いました。ヘパリンによる抗凝固療法を開始しましたが、入院3日目の夜間に胸痛が出現しました。心電図でV2-6誘導に新規の陰性T波が出現し、トロポニンIの再上昇が認め、心エコー図検査では新規に後壁基部に局所壁運動低下が出現し、既知の壁運動低下は一部改善を認めました。冠動脈CT検査上の造影欠損部の壁運動は改善しませんでしたが、前壁中部では改善を認め、塞栓の関与が疑われました。これらの変化から一連の経過として僧帽弁の疣腫を含めたTrousseau症候群からの冠動脈塞栓および再開通が疑われました。塞栓イベントの再発であり、心臓手術も考慮されましたが、画像検査上遠隔転移はなく、Stage Iの卵巣腫瘍によるものであり、手術を施行することで塞栓の再発軽減につながると考えられました。婦人科腫瘍手術が可能な高度医療機関へ転院し、両側付属器摘出術が施行されました。病理検査の結果、明細胞癌Stage IAと診断され、術後化学療法が行われました。引き続きヘパリンが継続され、定期的に心エコー図検査が施行されましたが、僧帽弁の疣腫は縮小傾向で新規の局所壁運動低下も認めませんでした。
NBTEは悪性腫瘍、自己免疫疾患、慢性消耗性疾患等を有する患者の心臓弁膜上に生じる、主にフィブリンと血小板からなる疣贅非感染性疣腫といわれています。担癌患者では脳梗塞の原因の16%を占め、合併しやすい悪性腫瘍としては肺癌、膵癌、胃癌等が挙げられます。剖検例の約1%、末期癌の4%、担癌患者の塞栓症症例では41%にみられ、診断後1年以内の死亡率が30%と予後不良です。ヘパリンを中心とした抗凝固療法が治療となりますが、経口抗凝固薬では血栓塞栓イベントの再発等の治療困難例が報告されています。
NBTEの疣贅による冠動脈塞栓の場合、脳血管塞栓に比べ小型の塞栓子が原因となり、微小塞栓に留まる傾向があることが報告されています。本症例で冠動脈の再還流を疑うような一部の壁運動の改善が見られたのは、上記のような微小塞栓が原因であったと考えられました。治療として原疾患の治療と、禁忌がなければヘパリンの静注もしくは皮下注を行うべきとされています。疣腫による急性心不全をきたす症例では手術を考慮する必要があります。本症例では10mm以上の疣腫で抗血栓療法導入後も冠動脈塞栓を疑うエピソードを認めましたが、再発の可能性や過凝固状態で塞栓が再燃する可能性があったことを考慮し、原疾患の治療を優先することとしました。
本症例を通して、左室壁運動が多発冠動脈塞栓に伴い経時的に変化したNBTEの一例を経験しました。NBTEはヘパリンが有効な治療法とされていますが、エビデンスは十分ではなく、本症例のように多発冠動脈塞栓の症例報告もわずかに認めるのみです。悪性腫瘍の進行や合併症により治療の選択肢が異なり、個々の症例で治療法を検討することが必要となります。
今回の経験を通してNBTEの病態、特に経時的な心機能の変化を捉える上で、心エコー図検査が非常に有用であることを改めて認識しました。また、多職種との連携が不可欠であることを痛感しました。今後もこのような貴重な経験を活かし、患者様にとって最善の医療を提供できるよう、日々精進していく所存です。
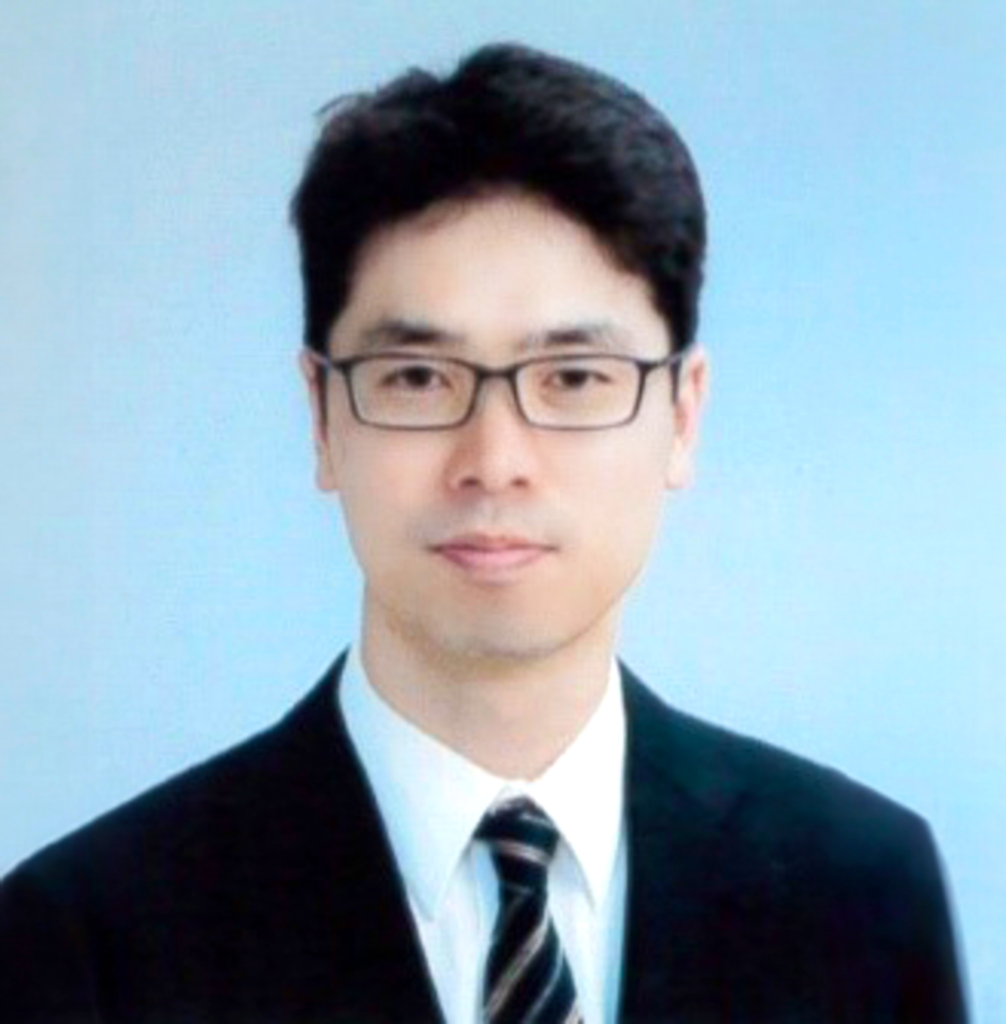
松浦 智弘(北播磨総合医療センター 循環器)





